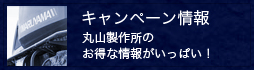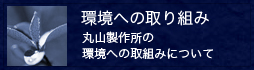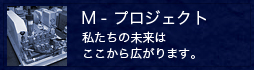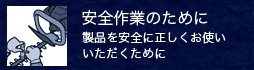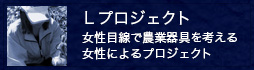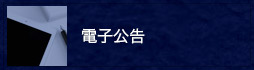丸山製作所グループの環境方針
地球温暖化、資源枯渇、環境汚染などの地球環境問題が依然として社会の深刻な問題となっています。当社グループは「誠意をもって人と事に當ろう」の経営理念、「人と環境の理想的な調和をめざして」のテーマのもと、地球環境保全活動にも積極的に取組んでいます。
丸山製作所グループの環境方針
株式会社丸山製作所は、「農業用機械、工業用機械、消防用機械」などを提供する事業を通じて、より豊かな社会に貢献するとともに地球環境負荷の低減に積極的に取り組みます。
1.環境管理のPDCAサイクルを確立・運用し、環境パフォーマンス向上を目的に継続的改善を図ります。
2.行政、利害関係者等からの環境関連の規制・規則・協定など順守します。
3.廃棄物の削減及びリサイクルを促進し、省資源・省エネルギー化を図り、またそれら環境に配慮した製品開発に取り組むことで地球温暖化、資源枯渇、環境汚染の低減及び環境保護に努めます。
4.従業員に対し、環境意識の向上のため、啓蒙活動を継続的に行います。
丸山製作所千葉工場はISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得しています。
| 登録社名 | 株式会社 丸山製作所 千葉工場 |
|---|---|
| 適用規格 | ISO 14001:2015/JIS Q 14001:2015 |
| 登録日 | 2001年 8月31日 |
| 登録更新日 | 2025年 8月31日 |
| 改訂日 | 2022年 8月31日 |
| 有効期限 | 2028年 8月30日 |
| 認証機関 | (一財)日本品質保証機構 |
| 登録証番号 | JQA-EM1743 |

「ISO14000の概略」
環境に関する国際規格ISO14000シリーズは企業が国際的に協調をとりながら、活動による地球環境への負荷を低減するツールとして、国際標準化機構(ISO)が1996年9月にシリーズの中核をなすISO14001を制定・発行され、2004年に一回目の改訂をし、2015年に附属書SLに基づき二回目の改訂がされ今日に至っています。
「認証取得への取り組み」
環境への関心が高まっている中で企業は,地球社会の中で「環境に対する負荷の軽減や環境に良い活動」を実施し、その取り組み姿勢や実施結果を地域や社会及び利害関係者に対して明確に報告できるような活動に取り組まなければならなくなってきました。このような流れを受けて、環境に関する活動のツールとしてISO14001が非常に有効であるという認識から認証取得活動を開始しました。
ISO14001はシステムの運用規格であり、企業における環境負荷を低減するための仕組みを企業に構築・運用することを求めたもので、法律や条例のような拘束力はありません。従って、環境ISOへの参加は任意であり、また、「自己宣言」(自らがISO14001規格の要求事項に適合していると宣言すること)も可能ですが、公平で客観的な第三者機関に規格への適合性の評価をゆだねることとし、JQA(日本品質保証機構)で登録審査を受審し、(株)丸山製作所 千葉工場として2001年8月に環境ISO14001の認証を取得いたしました。
「千葉工場の活動」
千葉工場の環境活動は環境に関する全ての計画のベースとなる環境方針に基づいて行われます。
現在の千葉工場の環境方針を次に示します。
株式会社丸山製作所千葉工場環境方針
株式会社丸山製作所千葉工場は、「農業用機械、工業用機械」などを提供する事業を通じて、より豊かな社会に貢献するとともに地球環境負荷の低減に積極的に取り組みます。
1.環境管理のPDCAサイクルを確立・運用し、環境パフォーマンス向上を目的に継続的改善を図ります。
2.行政、利害関係者等からの環境関連の規制・規則・協定など順守します。
3.廃棄物の削減及びリサイクルを促進し、省資源・省エネルギー化を図り、またそれら環境に配慮した製品開発に取り組むことで地球温暖化、資源枯渇、環境汚染の低減及び環境保護に努めます。
4.従業員に対し、環境意識の向上のため、啓蒙活動を継続的に行います。
千葉工場長
大平 康介
2021年10月1日
「適用範囲」
組織名称:株式会社丸山製作所 千葉工場
所在地:〒283-0044 千葉県東金市小沼田1554-3
活動範囲:農林業用機械、環境衛生用機械、工業用ポンプの開発・設計、製造、販売及びサービス
丸山製作所グループは地球環境保全活動に取組んでおり、その一環としてグリーン調達活動にも積極的に取組んでいます。丸山製作所ではグリーン調達ガイドラインを定め、このガイドラインに従った調達活動をしています。
グリーン調達は取引先様のご協力なくしては成り立ちません。丸山製作所グループの方針をご理解いただき、ご支援ご協力をお願いいたします。
2001年 4月 1日から、資源有効利用促進法(改正リサイクル法)の施行により、使用済み小型二次電池(繰り返し充電ができる蓄電池)の回収・リサイクルが電池メーカーおよび当該電池を使用する機器メーカーに義務付けられました。
丸山製作所もバッテリー噴霧機で小型二次電池を使用しており、資源有効利用促進法に基づき「一般社団法人JBRC」に加盟し、共同回収・リサイクル推進活動に協力しています。 使用済み小型二次電池の回収にご協力くださいますようお願い申し上げます。
小型二次電池の回収・リサイクルのご案内

回収対象となる小型二次電池

対象となる電池には、上記の識別のマーク、または、文字の表示がついております。
回収方法について
『充電式電池リサイクルボックス』のあるリサイクル協力店にお持ちください。 又は、購入店・弊社営業所でもお引取りいたします。 リサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
【お持ちいただく際の注意事項】
ショートによる発煙、発火の恐れがありますので絶縁のために端子にテープを貼ってください。 また、充電式鉛蓄電池はこのシステムでは回収できませんのでご注意ください。
【関連リンク】
エンジンの排ガス規制の歴史は、1970年代に自動車での公害問題をきっかけとした排ガス規制が始まりました。その後、自動車の規制が強化されるに従い、自動車以外のエンジン(ノンロードエンジン)の排ガス寄与率が相対的に増大し、1990年代の米国カリフォルニア州の規制を皮切りに世界各国でノンロードエンジンに対する排ガス規制がスタートしました。丸山製作所の2サイクルエンジンも各国の規制にクリアしたエンジンを生産しており、また、2サイクル以外のエンジンも各規制値をクリアしたエンジンを搭載しています。
2サイクルエンジンの排ガス規制の方法
日本では、社団法人日本陸用内燃機関協会が定める業界自主規制となっています。アメリカでは、EPA(米国の環境保護庁)よる法規制、ヨーロッパでは欧州連合加盟国がEC指令(その内容を加盟国が各国法にするよう求める指令)で規制されています。
刈払機等に搭載している2サイクルエンジンは、カテゴリーでは「携帯型」に属し、排気量別に3クラスに分かれており、HC+Nox/COの排出量で規制されています。
HC+Nox:炭化水素+窒素化合物の合計排出量
CO 一酸化炭素
排出量 g/kWh:エンジン1kW当たり1時間運転した際の当該物質の排出量(グラム)。
当社2サイクルエンジンも業界自主規制に準じた排出ガスレベルを達成しています。
携帯型2サイクルエンジン搭載機種の一例

日本陸用内燃機関協会が定める自主規制値
3次基準値(インユース規制(注2))
| エンジンクラス | 排気量(cc) | HC+NOx(g/kW-hr) | CO(g/kW-hr) | |
|---|---|---|---|---|
| 非携帯機器用 エンジン |
I | 225未満 | 10.0(注1) | 610 |
| II | 225以上 | 8.0 | 610 | |
| 携帯機器用 エンジン |
III | 20未満 | 50 | 805 |
| IIV | 20以上50未満 | 50 | 805 | |
| V | 50以上 | 72 | 603 |
(注1)
①排気量80cc以下のエンジンは、各エンジンクラス毎に設定された携帯機器用エンジン(HH)の排出ガス規制値を適用する。
②排気量80ccを超え140cc未満のエンジンの規制値は、当初13.1g/kW・hrとし、当初規制値導入効果の確認、移行時期の検討を行ったうえで、EPA3次規制同等の10.0 g/kW・hrへ移行する。
規制値10.0g/kW・hrへの移行は2019年1月を目標とする。
(注2)
インユース規制とは、予め定められた累積運転時間内は自主規制値をクリヤーしなければならないことを指す。
自主規制に対応したエンジンには次のマークが添付されています

丸山製作所の規制対応
エンジン開発部門では、この規制値をクリアするために排出ガスの後処理をすることない技術の開発に取組んでまいりました。
![]() M-プロジェクトへのリンク(環境対応排ガスエンジン)
M-プロジェクトへのリンク(環境対応排ガスエンジン)
<参考>2サイクルエンジン以外の搭載エンジン
ガソリン4サイクルエンジンやディーゼルエンジンにおきましても、自社開発は行っておりませんが、環境対応エンジンを搭載しております。
4サイクルガソリンエンジン及び定格出力19kW以下のディーゼルエンジン
2サイクルエンジンと同様に日本陸用内燃機関協会による業界自主規制

19kW以上のディーゼルエンジン
道路運送車両法,特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律(法規制)

【関連リンク】